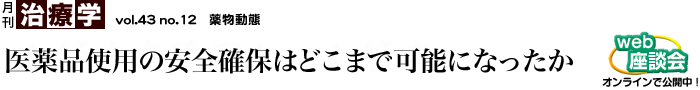
北田 実際に薬物を処方する医師は,遺伝的な背景による個人差にどう留意したらよいか,おうかがいしたいと思います。
東 たとえばワルファリンでは,同じ投与量であっても,個人間で薬効が異なるのは,2 つの因子で規定されているからです。 1 つはワルファリンの代謝酵素の CYP2C9 で,もう 1 つはビタミン K サイクルの vitamin K epoxide reductase complex 1(VKORC1)という酵素の多型です。 VKORC1 には A と G という 2 つのアレルタイプがあり,G をもつ人は酵素活性が高く,投与量が多くなります。 日本人では頻度が少ないのですが,Caucasian では 50%以上を占めています。 ワルファリンの投与量が日本人と欧米人とで異なるのは,体格や食生活などが原因であると言われていましたが,現在は,この VKORC1 の G をもつ人の頻度が高いためだと考えられています。
さらに,実際に医師がワルファリンを投与する場合,日本人ではワルファリン量が 1 日 2〜3 mg ですが, G アレルをもつ人は 6〜8 mg 投与しないと目的とするプロトロンビン時間(PT−INR)値になりません。 そのため,CYP2C9 の代謝活性を阻害する,非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の一種であるブコロームが併用される場合があります。 すると,ワルファリン 2 mg 程度でも目的とする PT−INR 値に達します。これは,薬物相互作用により CYP2C9 の PM をつくっていることになります。 しかし,この状態は非常に不安定です。ブコロームは CYP2C9 を阻害すると同時に,ワルファリンの血漿蛋白との結合置換も起こすという作用をもっています。 併用によりワルファリンの投与量を減らせますが,PT−INR 値が不安定になるという問題があります。 遺伝子判定を行い,患者さんに「VKORC1 の G タイプだから,投与量が多くてもよいのです」と説明する。そうなれば,医師も,患者も,安心してワルファリンの高用量を使用できます。
もう 1 点,PT−INR は 1.5 以上を維持されることによってワルファリンの抗凝固作用が現れますが,実際に調べてみますと,1.5 以下の人が 2 割程度いました。 処方する医師も投与量を増やすことを恐れて,最低限の薬物量しか処方していないので,ワルファリンの効果が十分得られていないことになります。 そういう患者さんの SNPs 解析をすると,VKORC1 は G タイプ保有者です。一方 CYP2C9 は,PM では,通常の半量以下でないと出血が起きる危険性が増します。 このように,遺伝子判定は臨床的なワルファリンの投与量を決められるので,有意義です。
北田 まれに起こる重篤な副作用,以前は特異体質性とされてきた有害作用では,遺伝的な背景が疑われます。 そのあたりで,最近明らかになったことをご紹介いただけますか。
池田 トログリタゾンの話に戻りますが,特別チームで,トログリタゾンで肝障害を起こした患者と,まったく起こさなかった患者の遺伝子診断を行いました。 薬物代謝酵素や,薬効に関係しそうなインスリン関係を調べたところ,唯一,統計学的に有意差の出てきたのがグルタチオン S トランスフェラーゼ(GST)という酵素でした。 これには何種類かあり,そのうちの T1,M1 という分子種,これらの両方とも活性のない, いわゆるダブルヌル(double null)というタイプの患者に有意差をもって肝障害が起きやすいことがわかりました。 肝障害が起きる理由は,GST は反応性代謝物を壊す酵素なので,その活性がないと,トログリタゾンからできた反応性代謝物を壊せないからです。 特別チームの成果のひとつとして,GST−T1 と GST−M1 の遺伝子診断により,肝障害を防ぐスキームが成り立ちました。
ところが,話はそれほど簡単ではありません。オッズ比を調べてもせいぜい 3.6 でした。3.6 は統計学的には明らかに有意差が出て,オッズ比としては高い数字ですが, その人たちに投与しなければ肝障害を 100%防げるかと言えば,そうではありません。 なぜなら,GST−T1 と M1 の両方の活性をもっていない人のなかにも,毒性の出ていない人がいました。 また,活性があっても毒性の出る人もいて,残念ながら,臨床的には使えませんでした。
トログリタゾンでこの論文が出たあと,2008 年にスペインのグループが,トログリタゾン以外の種々の薬物で肝障害の出た患者の GST−T1 と M1 のダブルヌルタイプを調べています。 有意差をもってダブルヌルタイプの患者で肝障害が出ていると,報告しています。その薬物のひとつはクラブラン酸アモキシシリンです。 これは,ダブルヌルではオッズ比が約 3 高くなり,イソニアジドでも同様だと報告されました。
それでは,臨床的にどうすべきか。「まあ,気をつけたほうがよいね」という程度にしかなりません。GST−T1 と M1 のダブルヌルに関しては,きわめて中途半端な扱いになっています。
池田 抗てんかん薬のカルバマゼピンでは,スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)という重篤な皮膚障害が起こります。 台湾の Dr. Chen のグループが,ヒト白血球抗原(HLA)の種々の SNPs との関連を調べ,臨床試験結果を報告しています。 漢民族で,HLA−B*1502 という SNPs をもっている患者では,オッズ比が 2504 というきわめて高い,驚異的な数字が出ました。 ここまでくると,HLA−B*1502 をもつ人すべてに投与しなければ,ほとんど 100%,副作用を防げることになります。
ただ HLA−B*1502 については,白人や日本人でも臨床試験が行われましたが,別の HLAの SNPs が関係しそうだという結果となりました。
すなわち,人種差があるので,毒性が出たときに,毒性の出た人とそうでない人を比較し,HLA のいろいろな SNPs を調べて, 各民族で,各薬物に独特な SNPs をみつければ,なんとかなりそうだというところまできています。
肝障害については,第一三共のグループが,Dr. Chen と同様な試験を HLA に関して行っています。 抗血小板薬のチクロピジンは,副作用として胆汁うっ滞性の肝障害が有名です。試験の結果,HLA−A*3303 をもっていると,有意に肝障害を起こし, オッズ比が 36.5 という明らかに高い数字が出ました。それでも 36.5 なので,HLA−A*3303 をもつ人に投与しなければ肝障害を 100%防げるかというと,そうではなさそうです。 これも,もどかしいという状況です。
ただ,この結果をもとに肝障害の発生率を減らすことは可能です。HLA−A*3303 をもつ人ではクロピドグレル(臨床試験中)と置き換えればよいのです。 チクロピジンを使わざるをえない状況では,HLA−A*3303 に留意しながら投与することになりますが。
鈴木 HLA−B*1502 とカルバマゼピンについてですが,HLA−B*1502 の配列をもつ日本人はほとんどいないので, この配列が日本人で問題になることはほとんどないものと考えられます。
鈴木 HLA−B*5801 については,アロプリノールで SJS の発生が報告されています。 これに関与する HLA−B*5801 は,漢民族,台湾人のなかで 17%を占めます。 すると,17%もの人にアロプリノールを投与しないわけにもいかないということになります。
このような知見は,薬物開発にも大きく関係してくるものと思います。 特定の HLA の配列をもっている場合には,免疫系の反応が亢進している可能性がありますので,今後創薬の段階で,この可能性を試験するようなシステムの構築が大切になると思います。 たとえば,ある HLA のタイプは,強直性脊椎炎発症の危険因子となるほか,HIV に感染後の AIDS 発症まで時間がかかる方々や,潰瘍性大腸炎の進行型の方々に観察されるなど, 免疫系機能の活性化に結びついていることが知られています。
このように,免疫系の反応が亢進している患者の場合には,代謝活性化された薬物が肝臓の蛋白質に結合して, ハプテン抗原のようなかたちで提示されて,免疫系が肝臓を攻撃するなどの仮説も考えられるものと思います。
池田 私もまったく同感です。たとえば,ウイルス性肝障害がありますが,肝炎ウイルスに感染しても肝障害を発症する人と,そうでない人がいます。 その理由はまだわかりません。ウイルスから蛋白ができて,断片化されて,異物として免疫系に提示されるわけですが,それを異物と認識するリンパ球がいるかいないか, それがおそらく HLA の SNPs に関係しているだろうと思います。まだ仮説の段階ですが, 薬物による SJS も,漢民族は HLA−B*5801 をもつ人が薬物で変性を受けた蛋白質を異物と認識するが, 日本人は別の HLA の SNPs をもった人がそれを異物と認識する。それを探さないといけないと,皆が思い始めているところだと思います。
北田 これまでは経験的なさじ加減で投与設計をしていましたが, 現在は,毒性や相互作用発現の機序の解明,それらの発現に影響する遺伝的背景などのエビデンスが蓄積し, より精度の高い,安全性の高い薬物治療の個別化が可能になってきています。 さらに,まだ一部ではありますが,これまでは予測できないとされてきた副作用も, 個人の遺伝的な背景によって,危険性の高い患者層をある程度,絞り込めるようになってきました。 100%ではありませんが,ゆくゆくはこの延長線上に,かなり確度の高い予測性が期待できるのではないかと思います。本日はありがとうございました。