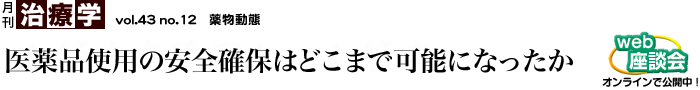
北田 近年,薬物治療は急速に進歩し,強力な医薬品が多数生み出されています。 その一方で,副作用の少ない安全な医薬品も強く求められていますが,現状では,副作用のない薬をつくることはなかなか困難なようです。
池田敏彦先生,医薬品開発時の苦労など,ご経験をうかがわせていただけますか。
池田 私はもと三共株式会社(現 第一三共株式会社)で,薬物動態の研究に携わっていました。 毒性の研究には関係がありませんでしたが,糖尿病治療薬のトログリタゾンの開発を契機に,毒性にも関わるようになりました。
トログリタゾンは,1997 年に世界初の経口糖尿病治療薬として世に出ました。 当初は拍手をもって市場に迎えられた薬でしたが,特異体質性の肝障害で緊急安全性情報が出て,その後には自主回収せざるをえない状況になりました。 当時,肝障害は,だれもが特異体質性だと考えていました。市場からの撤退時に,開発した会社として原因を解明すべきだと,独立チームが編成され,私も参加しました。
原因として種々の可能性が考えられましたが,なかでも反応性代謝物が議論されました。1970 年代に米国 NIH(国立衛生研究所)のグループが, アセトアミノフェンの反応性代謝物について報告して以来,問題であるとされていました。 アセトアミノフェンの場合には,多量に服用すれば,体質にかかわらず,だれにでも毒性が必ず出て,アセトアミノフェンの特徴だとされました。 その特徴が,反応性代謝物に由来しているとされたのです。
しかし,われわれはトログリタゾンにこの考え方が適用できるとは思っていませんでした。 なぜなら,トログリタゾンはグルクロン酸抱合と硫酸抱合により,代謝がほぼ 100%説明できるからで,反応性代謝物ができるとは夢にも思っていませんでした。 ところが,14C 標識体で標識したトログリタゾンで実験を行うと,共有結合をする反応性代謝物が生じていたのです。 特異体質性の毒性も,反応性代謝物が関与しているという仮説が立てられましたが,トログリタゾンでは,何万人に 1 人の特異体質の人にのみ毒性が現れ,その理由がまったく不明でした。
その後,特別チームは,患者の遺伝子解析を行う方向へと展開していきました。特異体質性の薬物毒性においても,反応性代謝物が最も重要だという認識は,世界共通になっています。
池田 前臨床,つまり動物実験の段階で,反応性代謝物をどう抑えるかという研究に移りました。 それには,反応性代謝物をどう検出するかが重要です。in vitro の実験で反応性代謝物を確認するには,2 つの方法があります。 1 つは,放射性標識化合物をつくり,蛋白質に共有結合した放射能の量を測定する方法です。 当時,メルク社(現 ワシントン大学)の Dr. Baillie が,50 pmol/mg 蛋白という in vitro のクライテリアを発表し,これを超えなければよいとされました。 50 という数値は低すぎるとも言われましたが,これを基準に判断することになったのです。
ただ,14C 標識体で標識するのは,開発後期の段階になります。より前の段階では,種々な方法があります。 ひとつは,薬物相互作用の利用です。たとえば mechanism based inhibition で,これが現れる薬剤ではたいてい反応性代謝物ができています。 mechanism based inhibition は,in vitro で蛍光標識基質を使用してハイスループットスクリーニングで検出できます。 フォールスネガティブも全部含めて,ひっかかった化合物にフラッグを立て,そのまま流していきます。 多数の化合物のなかからどんどん絞り込みを行い,5 つくらいになった段階で,mechanism based inhibition が起きるものはいずれは反応性代謝物をつくるのだからと中止して, そうでないものをリード化合物にするという考えです。リード化合物の候補が絞り込まれたら, そこで 14C 標識体をつくり,50 pmol/mg 蛋白をクライテリアとして,さらに絞り込むという,流れになっています。
もう 1 つ,in vivo のクライテリアもできています。臨床的な観察によるもので, トロント大学の Dr. Uetrecht が 10 mg/body を超えない薬は肝毒性も含め,特異体質性の薬物毒性がほとんど発生していないと報告しました。
通常,種々の動物実験からヒトの臨床投与量をある程度,推定することが可能です。 そのときに,10 mg/body を超えるか超えないかという基準を適用して化合物をふるい分けすることも行われるようになってきつつあります。
北田 現在の薬物は,切れ味が鋭く,少量で効果があり,使い方によっては怖いという印象さえ受けます。 微量になったことで,そのすべてが活性化代謝物になったとしても,先ほどの 50 pmol/mg 蛋白を超えなければ安全性は高いと判断してよいということでしょうか。
池田 ええ。吸収性の問題がありますが,それは別にして,薬理学的に比活性の高い, したがって低用量で薬効の高い,in vivo で服用量の少ない薬物が,安全性のうえからも求められるのです。